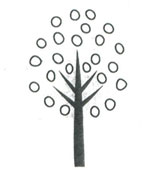 看護実習生の記録より 看護実習生の記録より
今年も高松市医師会看護専門学校から31名(うち8名男性)が6月22日から7月14日まで実習に来ました。当園の卒園生や保護者の方もいて、国家資格を目指して、熱心に勉学に励んでいます。当園の実習で学んだこと気づいたこと各クラス別に皆様にご紹介しましょう。
◎ことり組(乳児)
あそびについて━━どんぐり体操や食事前の絵本の読み聞かせ、手遊び歌などを行っていた。音楽がかかると大人のまねをして踊ったり、声を出したり大人の動きをじっと観察したりと様々であった。
乳児期は首の座りから座位、立位へと姿勢の保持能力が進むので能力を合わせて筋力やバランス感覚の発達を促すよう運動を働きかけていた。

◎つくし組(1歳)
衣服について━━幼児の運動量は増大し、衣服の汚れや損傷はひどくなるので上部で吸湿性の高い素材を選ぶ必要がある。また、自分で着脱することに興味を持つので幼児が扱いやすいものが望ましい。(例:前開き、ボタンが大きい、ボタンの数も少ない、シンプルなデザイン)
感触あそび━━小麦粉でできたドロドロした粘土を触り、感覚の刺激を楽しむ遊びである。五感を刺激することは脳の発達に影響を与える。また、したことのない経験をすることで、興味関心を高めることにつながっている。
◎はと組(1歳)
運動あそび━━感覚技能や運動技能を働かせること、喜ぶ遊びを乳児期を中心に1歳半頃から始まる。1歳半頃は前後歩きやジャンプ、1歳9か月頃には手すりを持って階段を昇ることができるようになり、2歳〜2歳半頃には両足を揃えながら階段を昇降できる。主に1人あそびがメインであるが、集団でのあそびの中で社会性を身に付けていく。
食事について━━1歳〜1歳半頃の幼児は手先の運動が発達することに伴って、自分の手で食物をつかんで楽しみながら口に運びスプーンやコップをつかうようになる。支えたり促したりは必要だが、食物をつかんで楽しみながら食事することが大切と理解した。

◎つぼみ青組(2歳)
前期健診について━━幼児期は見慣れない人や物、普段と違う行動に対して不安を感じ、泣いたり叫んだり時には逃げ出したりすることがある。園児の恐怖心や不安を取り除くために保育者から健診で医師がどんなことを行うか1人の園児をモデルにデモストレーションを行っていた。また、不安で泣いたりしてしまうと心臓の音が聞きとれなくて医師が困ると説明を行っていた。実際に健診を行う際には、保育者が1人付き添って服を持ち上げたりの介助を行い、終わった後には「よくがんばったね。」と園児1人1人とを褒めていた。始まるまでは怖がって泣いていた子どももいたが、ほとんどの園児は保育者からのデモストレーションがあったので、泣くことなく行えていた。
◎つぼみ赤組(2歳)
トイレトレーニング━━決まった時間にトイレに誘導してみることでトイレで排泄する習慣を身に付けることができ、友達が上手にトイレで排泄している様子を見ることは、排泄の行動を獲得する上で大切であると学んだ。
また、排泄後自分でパンツとオムツを履くことができるよう全てを手伝うのではなく、園児のできない部分のみを手伝ったり、やり方を教えたりして自立を促すことの大切さを理解した。排泄後の手洗いについても声かけをすることで自ら手洗いが出来ており、声かけや見守ることの大切さを学んだ。

◎さくら組(3歳)
あそび━━各自がしたいことを見守る自我の発達に伴って自分のあそびの種類を選択したり、自分なりの遊び方を見つけたりしているため必要以上に干渉することは、自発性を妨げてしまうことにつながるため本人の意見を尊重することが望ましい。また、自分で玩具を片付けることに興味を示すため、使い終わった玩具の整理整頓は積極的に促すことが自主性、自律性を発達させるために有効であることを学べた。
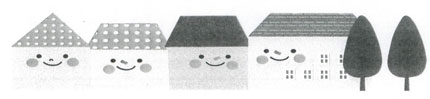
◎ほし組(4歳)
おひるね━━4歳ごろになると成長に従い、睡眠時間は短くなり、無理にひるねをさせ過ぎるのも夜の寝つきが悪くなったり睡眠の質が下がる可能性があり、個別性が必要であるが、ほし組では1時間程での短時間の睡眠時間であり、この1時間程で得られる効果は体や脳の疲れを癒したり、記憶力の向上や情緒の安定にもプラスとして働く大きなメリットがあり、日中に様々な刺激を受けた脳をクールダウンさせて、一旦リセットすることで再び元気に活動できる効果があると考えた。

◎すみれ組(5歳〜6歳)
鍵盤ハーモニカ練習について━━鍵盤ハーモニカ練習を始めた直後は先生の話や指示を聞くことが出来ていたが経過とともに先生の話が聞けなくなっていく子がいた。幼児が何か1つのことに注意を向けていられる時間は短く、5歳頃では30分程度であり個人差も強く出る。また、注意を向けることが出来なくなるのは鍵盤ハーモニカをうまく弾けない様子の子が多く、興味喪失によるところも大きいと考えられる。鍵盤を弾く指の動きから微細運動の発達が正常にできていると考えられる。
|