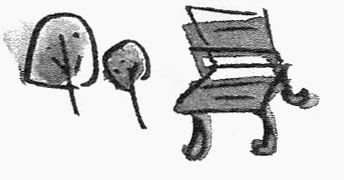~ Vol.364 ~
~ Vol.364 ~
どうしても頑張れない人たち
宮口 幸治
プロフィール
立命館大学産業社会学部教授。医学博士、精神科医、臨床心理士。精神科病院、医療少年院での勤務を経て2016年より現職。著書に『ケーキの切れない非行少年たち』及びコミックス1巻2巻などがある。
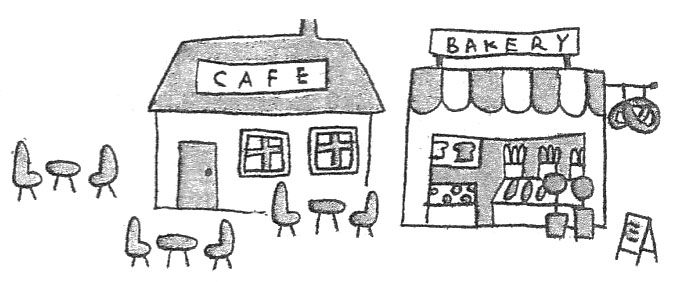
○はじめに
子どもを虐待してしまった親は、時には支援者に攻撃的にすらなります。支援者が罵倒されることもあるかもしれません。そういった場合、支援者としてもどうしてもネガティブな気持ちになり、あまり関わりたくない、支援したくないといった感情が出てくるのも無理からぬところでしょう。しかし、真実を言えば、〝支援したくないような相手だからこそ支援しなければいけない〟のです。
成績優秀者に給付される奨学金制度もしかりです。頑張って奨学金を取れる学生は、それはそれでいいとしても、頑張ってもそういった奨学金を取れない学生がアルバイトに明け暮れ、学業が疎かになり、単位を落としたりして、ますます悪循環に至っているのを知るにつけ、むしろ奨学金を取れない学生にこそ奨学金を与えて支援したほうがいいのではないか、と密かに感じています。
また〝頑張っている人を応援します〟はよく聞くキャッチコピーですが、〝怠けている人を応援します〟とはなかなか聞かないでしょう。一方で、実際は頑張っても頑張れないので、どうしても怠けてしまっているように見えているケースもあります。この場合も同様に、〝怠けているからこそ応援しなければいけない〟のです。
そういった人たちへの支援をどうしていけばいいのか、については、現代社会においてこれから考えていかねばならない課題だと思います。現実が矛盾だらけであることは承知していますが、やはり〝頑張れない人たちにも頑張ってほしい〟という気持ちがあります。
頑張れない人たち自身にも、頑張って〝社会から評価されたい〟気持ちもきっとあるはずです。元受刑者を受け入れている会社の中には、彼らが頑張れなくても何度もチャンスを与えて、決して見捨てることなく伴走し支援されている方々もおられます。何度も何度も裏切り続けた少年を決して見捨てることなく、更生に導いた幾つかの取り組みもあります。こうした事例を知るにつけ、頑張れない人たちもいつかは頑張れるようになるのではと希望を抱かずにはいられません。
〇場違いな褒め言葉
褒めること自体を否定するものではありませんが、ここではもう一歩進めて、褒めることで逆に子どものやる気や保護者の気持ちを奪ってしまう例をご紹介します。それらが「場違いな褒め言葉」です。
例えば、自分が嫌いな人をひとり思い浮かべて下さい。彼、ないし彼女からどうでもいいようなことで褒められたとしたら、いかがでしょうか。あなたがたまたまゴミを拾っているところを見られ、「君は素晴らしい」と褒められたとしたら? 曖昧にしか聞こえないでしょう。
相手の状況も知らずに褒めることは、逆効果になることもあります。例えば保護者が色々と悩んだ挙句、学校の先生に「うちの子はこんなに大変なんです」といった感じで子どもの相談をした際に、「〇〇君はとてもいい子ですよ。優しいところがあって。この前も‥‥」と返したりする場合です。タイミングによってはうまくいくケースもあると思いますが、保護者は〝この先生は息子のことを何も分かってくれていない〟と逆に不信感をもつこともありえます。
この場合の保護者は、具体的な相談をしたいというよりも、まずは子どもの状態について共感してほしい、自分のしんどさ、大変さを分かってほしい、といった思いを強く持っていただけかも知れません。だとすれば、子どもを褒めるよりも親に対する共感の言葉の方が響くはずです。このケースで安易に子どものことを褒めてしまうと、親のやる気を奪ってしまうことにも繋がり兼ねないのです。
〇〝親の愛情不足では?〟という言葉の凶器
私はこれまで、さまざまな子どものためのケースカンファレンスや研修会に
出ていますが、子どもに何か問題行動があった場合、大抵この〝親の愛情不足では?〟という意見が出てきます。悲しいことに、それを聞いてみんな「そうかぁ
‥‥」と安心してしまうのです。
支援者は、寂しさから不適応を起こしているかもしれない子どもを目の前にすると、親に対してつい、〝子どもにもっと愛情をかけて欲しい〟〝愛情が不足しているのでは?〟といった気持ちをもってしまいます。さらにそう思う背景には〝親が仕事ばかりで子どもがいつも一人ぼっちだ〟〝子どもにかまってあげていない〟といった憶測もあったりします。しかし、程度がどうであれ、頑張ろうとまったく思っていない親などほとんどいません。それでも、どうしようもないような状況に追い込まれていることもあります。
親も子育てに不安を感じています。仕事が大変でも、子どもに寂しい思いをさ
せないよう、周りからもそう思われないよう、気を遣っているところもあります。そのような状況の中で、さらに〝愛情不足では?〟とまで言われたら、それは何の解決にもならないどころか、余計に親を追い詰める凶器になるのです。
〇こどもに近い保護者を支えよ
支援者自身が相手のために頑張るぞという気持ちになれることが大切です。子どもを支援する上で一番の効果的な支援は何かと言えば、その子の保護者に“この子のために頑張ろう”と思ってもらうことなのです。
そのためにはどうするか。少年院ではまず保護者に労いの言葉をかけます。
「これまで子育てご苦労さまでした。大変苦労されたことでしょう。これからは我々に任せてください」
そう伝えます。少年院にきて「また教官から責められたり指導を受けたりするのか」と思っていた保護者は、ホロリとするようです。少年院側も、とにかく保護者に元気になってもらうことが目的ですので、少年院に入っている時の保護者会では少年たちの問題点はまだ伝えません。まずは保護者を、少年を支える誰よりも大切な人として尊重するのです。
〇保護者のやり方を無理に変えようとしない
・基本的には保護者のやり方を否定しない
・無理に保護者を変えようとせず、子どもの成長を目標にする
今さら他者から言われて変わるくらいなら、とっくに変わっていたはずです。むしろ、長年、家族内で試行錯誤をしてきたことでうまくいったこともあるはずなので、逆にそのような保護者の対応を支援のヒントにしていく方が、お互いにとっても有益なのです。
〇保護者が変わったと思われるきっかけ
・保護者自身の体験が認められたとき
・信頼できる人が見つかったとき
・子どもに変化がみられたとき(感謝のことばを言うようになった)
・子どもにとっての自分の役割が分かったとき(面会を喜んでくれる。まだ自分もできることが残っている)