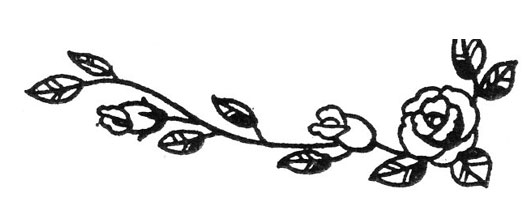~ Vol.348 ~
~ Vol.348 ~
「仏教保育目標」に対する職員のエピソード記録より
おうまのおやこ」11月号に続いて仏教園である当園が、毎月の仏教保育目標を日常の保育にどう生かしているかを
エピソードとして報告しあっています。
それを令和5年7月~9月までをご紹介しましょう。
7月 保育目標:布施奉仕
(どんな時でも、思いやりや親切な心を尽くしましょう)
〇 毎日園庭で元気に遊ぶ子どもたち。ある日大きな三輪車に乗りたいけれど、全部友達が使っていて、無理やり乗ろうとしてトラブル発生。「違うのもあるよ。」と声をかけるが、どうしても大きいのに乗りたいようで泣き出した。すると側で様子をうかがっていた大きい三輪車に乗った女の子がそっと降りて、その子に自分の三輪車を渡していた。自分の乗りたい気持ちより、泣いている子の気持ちを思って譲ってあげたAちゃん。「ありがとうね。」と声をかけると満面の笑みで満足そうだった。(1歳児担当)

〇 延長保育の時間に、1歳児のクラスの子がその部屋に行くと、いつも年長児が出迎えてくれたり、おやつとなると水筒のセッティングや、手洗いを一緒にしてあげたり、お菓子の袋を開けてあげたりといつもお世話をしてくれます。それを見て負けじとお世話しようとする3.4歳児の子もいます。同年齢の子たちと過ごす時は元気いっぱいで、少しやんちゃな様子が見られる子でも、こんなにも小さい子を思いやり、やさしく接する姿が見られたこと、きっとこの思いやりがまた、今1歳の子が大きくなった時に、小さい子へやさしく接し、続けていくんだろうなぁ…と思ったりします。 また、私自身が昼食を部屋に運ぶ時に、トレーを両手で持っていると、そばにいた年長児が、それに気づき、戸を開けて「どうぞ。」と言ってくれたことがありました。言わなくても気づき、通してくれたことがとても嬉しく、「ありがとう。」と言うと、その子もとても嬉しそうでした。職員同士でもいろんな「おたがいさま」に助けられたり、救われたりしている毎日で日々ありがたいなと感じています。(2歳児担当)
〇 毎朝「人数当番にきました。」と各クラスをまわってくれているすみれ組のお当番さん。初めの頃は恥ずかしそうにしたり、まごついたりしていたけど、もう何回目かになり、ずいぶんと慣れてきたように思う。 誰かにありがとうと言われるためではなく、みんなのために頑張っている子どもたちを見ると、すごく素敵だなぁと思うし、「ありがとう。お願いします。」と言って送り出したいと思う。自分も今の仕事場で何ができるのかをよく考え、人の役に立てるようにしていきたい。(フリー担当))

8月 保育目標 : 自利利他
(相手を思う心がけや行動が、自分の救いとなります)
〇 4、5月とよくお友達に噛みついたり、「やめようね。」という保育者の言葉を聞き入れられなかったY君。とっても甘えん坊で抱っこしてほしいとアピールしたり、一緒に好きなおもちゃで遊ぶと、めちゃくちゃ嬉しそうな表情をする。私達とのスキンシップや一緒に遊ぶことによっての信頼関係が出来てくると、自然と噛みつきも少なくなった。自分の思いを分かってくれるという安心感から、心のざわつきも無くなったのかな…と感じた。まだまだ絵本の取り合いなどトラブルも多いが、少し待つやゆずるという気持ちも見え隠れしているので、1対1で関わる時間も作りながら、成長を手助けできる言葉がけや、おおらかに気長に待ってみるということも意識し、保育していきたい。(1歳児担当)
〇 土曜日は0歳~5歳までの異年齢保育である。車を並べて遊んでいた5歳児の男の子。0、1歳の子が側に来て、取ろうとしたり取ったりすると怒鳴ったり、取り返したりおもちゃを抱えこんだりする姿が以前はよく見られたが、この日は、怒ることなく「これがいる?」「いいよ。」と言って貸してあげ、何回も自分の遊びを邪魔されるが、「小さい子には優しくね。」と言いながら遊んでいた。自分が我慢しながらも相手に優しく接することで、相手が嬉しそうにしたりすると自分も笑顔になり、嬉しそうにしていた。自分だけがいいようにするのではなく、相手のことを思って行動し、それが自分の幸せに繋がっていくという自利利他だと感じた。(フリー担当)
〇 今まで全ての保育者がやっていた片付けだが、子どもの前に箱を持って行ったり、手を添えたりすると入れられるようになってきた。まだ種類別に分けるのは難しく、とりあえず箱や棚に戻せたら良しとしているが、お供えのようにままごとの食べものがポツンポツンと置かれていたり、もうしまっている箱から取って別の箱に入れるなど一生懸命な姿が見られた。(乳児担当)

9月 保育目標:報恩感謝
(色々な人や物ごとのいいことも悪いことも、縁あってのことだと感謝します)
〇 日頃より「ありがとう」「ごめんなさい」について、子どもたちと考えることがあります。「ごめんなさい」は悪いことをした時にだけ言う言葉ではなく、わざとぶつかったんじゃなくても「ごめんね」と言ってもらえると心がホッコリするよね。と話していました。ある日、おもちゃを貸してもらった子が「ありがとう」と言えた時「ぽっこり(ホッコリ)ね。」と言っている姿に感謝の気持ちは子どもたちにもしっかり伝わっているんだなぁと嬉しくなりました。(2歳児担当)
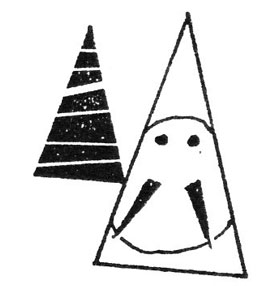
〇 子ども : 夏にきゅうりをクラスで育てている時には、自分たちで水やりをし、きゅうりの収穫をして、水の大切さ、野菜への感謝から「水やりをしよう。」「どれだけ大きくなったかな。」と野菜を観察しに行っていたが、きゅうりの時期が終わり、収穫できなくなると野菜を見に行く子どもが少なくなった。しかし、9月に入り、ピーマンや秋ナスが少しずつ大きくなって来て収穫できるようになるとまた、子どもたちが野菜に興味を持ち始め、水やりをしたり、観察をしたりするようになった。自分たちで野菜を育ててくれている方々への感謝の気持ちに気付いたことで、苦手な野菜が給食に出てきても感謝して、一口だけでも食べようとする子どもたちの姿が見られた。
保育者 : 1日の中で、他の先生に助けていただいた時や、他の先生が先に気付き、記入してくれていたり、提出してくれていた時などちょっとした些細なことでも、「ありがとう」の気持ちを大切にし、自分の心の中だけで止めるのではなく、声に出して言葉にして「ありがとう」を伝えることを心がけた。他の保育者にだけでなく、子どもたちに対しても、「ありがとう」を言葉にして伝えることで、こどもたちからも「ありがとう」の言葉が聞こえてくるようになった。(3歳児担当)
〇 1人の子が転んでしまい、泣いている。それを見た1人の子が近づいてきて「大丈夫?」と聞く。頭をなでながら、顔をのぞきこんでいる。泣いていた子は泣き止み、「ありがとう」と言って走り出した。なかなか自分から「ありがとう」と言えなかった子が素直に言えるようになり、嬉しく感じた。また、友達っていいなとその子が気付いてくれたようでよかったと思った。 (2歳児担当)