|

だから電気はおもしろい
細川 真由美
ドアの取っ手で「ビリッ」(静電気の話)
冬になって、ひんぱんに静電気の攻撃を受けるようになりました。
出入り口のドアの取っ手に手をのばせば「ビリッ」、車のドアで「バシッ」と、あちこちでビリバシしっ放しの私です。
静電気の衝撃は、ほんの一瞬で終わりますが、あまり気持ちのいいものではありませんし、 いつまでたっても慣れて平気になることはなさそうです。
ビリバシするたびに「うわっ」とさけびたくなるのですが、 いい大人がひとり騒ぐのも恥ずかしいのでじっとがまんをしています。
静電気は、人間のちょっとした動作で発生します。着ている服がこすれて、静電気はだんだん体にたまっていきます。
そして、たまった静電気が、体の外へ流れ出る道をみつけて、出ていくときに「バチッ」と指先などに衝撃を与えることがあるのです。
体を動かさずにじっとしていれば、静電気は少なくなるのでしょうが、そういうわけにもいきません。
湿度が高ければ自然に放電して、人体にたまる静電気の量は少なくなり、湿度55%以上になると静電気は発生しないそうです。乾燥していると静電気がたまりやすくなります。
着ている服のせいで、男性より女性のほうが静電気を帯びやすいそうですが、それにしても私は他の人よりもビリバシしている気がします。私の冬の必須アイテム、ばばシャツのせいでしょうか。
重ね着した服の繊維が、同種のものだと静電気は起きにくいのですが、たとえばナイロンとアクリルとか異種の繊維がこすれ合うと静電気が起きやすくなります。
私が今日着ていたばばシャツを確認してみると、アクリル、レーヨン、ナイロン、ポリウレタンの混紡でした。これでは上に何を着てもビリバシしそうです。
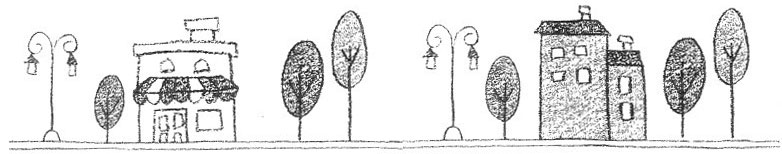
他の人に触ったときにも「ビリッ」とくることがあります。
何気なくお互いの手が触れた瞬間、「バシッ」とけっこう強い衝撃がきて、お互いに「うわっ」とのけぞったこともありました。仲のいい友人なので、火花を散らす相手でもなかったのですが…。そばにいる人に無意識に、静電気で電撃パンチを与えてしまうことがあるのは困りものです。
セーターを脱ぐときのビリビリバチバチの集中攻撃は、約3000〜5000ボルトという高い電圧になっています。でも電流はわずかなので、私たちは少し痛みを感じる程度です。ちなみに静電気の場合、3000ボルトぐらいまでなら痛みを感じないとのこと。
ところで、静電気の大親分の雷は、数億ボルトとスケールがちがいます。
雷は、おおまかに言うと、空気中の水や氷の粒がこすれ合うことにより発生した静電気が雲にたまり、放電する現象です。
「雷って夏の話よね」と思っている四国育ちの私たちには意外ですが、日本海側は冬の雷のほうが多いそうです。
気象庁の資料によると、夏の雷と冬の雷は放電のようすがちがい、夏は激しい雷雨となり、数秒間隔で発雷して2〜3時間継続することがありますが、冬は激しい雷になることはめったにないとのことです。
また、冬は対流活動が夏に比べて弱いので、 一度放電すると次の放電まで時間がかかり、 30分以上の間隔になることもあり、「一発雷」とも言われます。そして、冬はエネルギーの大きな放電の割合が高く、落雷した場合には、夏より大きな被害をもたらす可能性が高いそうです。
大親分の雷を筆頭に、悪さばかりしている静電気ですが、ここで生活に役立っている静電気も紹介しておきましよう。
まずは私たちが大変な恩恵を受けているオフィスに欠かせないコピー機には、静電気が利用されています。1938年にアメリカのカールソンという人によって発明されたそうです。
また、家庭で大活躍の食品用ラップは、ロールからはがすときに生じる静電気で容器とラップを密着させています。
そして静電集じん装置や静電塗装などにも静電気が利用されています。
今はまったく見通しがないようですが、雷のエネルギーが利用できたら、世界のエネルギー事情は大きく変わるでしよう。
世界中で毎秒100個の落雷があって、1回の落雷で、家庭用の電力消費量にして1世帯あたりで2カ月分くらいのエネルギーになるそうです。

平賀源内先生遺品館へ
平賀源内先生遺品館へ行きました。
源内さんは、高松藩の軽輩御蔵番の子として1728年に讃岐志度浦に生まれています。その旧邸が遺品館になっています。
遺品館は小さな建物ですが、見ごたえのある展示品がありました。
今現存している源内作のエレキテルの2つのうちの1つが、この遺品館にありました。
源内さんは、長崎でオランダ製の壊れたエレキテルを手に入れ、これを7年後に復元したとのこと。エレキテルとは、摩擦静電気の発生装置。
オランダで発明され、見世物や医療器具(効果はあやしい?)として用いられていたそう。
木製の箱型の内部に蓄電器があり、外付けのハンドルを回すと内部でガラスが摩擦され、発生した電気が銅線へ伝わって放電するしくみ。
遺品館には、エレキテルと同じしくみの装置があって、案内してくださった方が「ハンドルを回してみてください」とおっしゃるので挑戦してみました。30回ほどハンドルを回すと火花が出たり、蛍光ランプを瞬間的に光らせたりすることができます。小学生の理科の実験のようで童心に戻って楽しむことができました。
2000年に朝日新聞が行った「この1000年『日本の科学者』読者人気投票」では、1位は野口英世、2位は湯川秀樹、3位が平賀源内でした。
科学者での堂々3位に驚きますが、源内さんは、発明家・文芸家・陶芸家・画家・本草家・起業家・鉱山家といろんな顔をもっていました。
土用の丑の日に鰻を食べる風習は、夏になると暑いので鰻が売れなくて困っていた鰻屋が源内さんに相談をもちかけ、「本日、土用丑の日」と書いた張り紙をしたら大繁盛したことがきっかけだということです。
また、今、世間を騒がせているアスベストにも関係しているのです。
源内さんはアスベストを秩父山中で発見し、火の中に入れると汚れだけ
が燃える「火浣布」と名づけて宣伝したとのことです。
広報誌「電気と保安」別冊『だから電気はおもしろい』より
【細川真由美(ほそかわまゆみ) 】
普通高校卒
昭和55年、四国電力入社。
第二種電気工事士、第一種電気工事士、電験三種、エネルギー管理士(電気)等の資格取得。
平成16年、四国電気保安協会に出向。現在、本部営業部開発グループ課長。
|